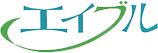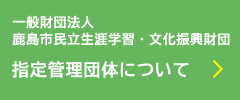「ふるさと」は、心にどのように刻み込まれるのだろうか。
ふ・る・さ・と
道端の田んぼに、わずかに咲くレンゲ草を見て、♬「ひいらいた/ひいらいた/レンゲの花が/ひいらいた」と歌っていたころを思い出した。(恥ずかしいことに、この歌のレンゲの花は、蓮の花の蓮華と最近になって知った。レンゲ草は開いたり閉じたりしないのに!)
あのころ、紅色のカーペットを敷きつめたように咲いていたレンゲ草を思い出す。
そこでは、女の子は、そのレンゲ草で首飾りや頭飾りを編むために、たくさんのレンゲ草を摘んでいたし、男の子は、手打ち野球といって、フワフワのボールを手で打って、走り、守ってその紅色のカーペットを踏みつけ夢中になって遊んでいた。
遊ぶ人数も多く、ゲームができた。田んぼは、遊び場だったのだ。
しかし、最近は、このレンゲ草もあまり見なくなったし、子どもも居なくなった。野山から、子どもがいなくなって久しい。
「ふるさと」とは、自分の足で踏みしめた大地ではないだろうか。自分の足で歩き、走り、動いて広げた、実感のある空間ではないだろうか。その意味からすると、今の子どもたちの「ふるさと」とは、どのような実感を持つのだろうか。
「うさぎ追いしかの山、こぶな釣りしかの川」のような実感は、無いのかもしれない。
理屈でもなく仮想空間(バーチャル)でもない、生の実感がないと「ふるさと」が、ぼやける。
エイブルの木6月号「エイブルからこんにちは」
館長 永池 守